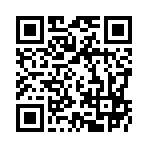☆「甲子園球場は聖地か?」
夏の高校野球が始まった。
元高校球児としては血が騒ぐ時期だ!
まずは、大会に出場された高校・選手には素直にお祝いを言いたい。
さらに、甲子園球場でプレーができる幸せを感じてほしい。
私は甲子園には出場していない。ハッキリ言って、出場できない選手のほうが圧倒的に多いのである。
甲子園に出場しただけで羨ましい。 だからこそ、楽しんでプレーしてほしい。
学校・郷土の期待はいやおうなしにあるだろうが、まずは選手自身が甲子園でプレーできる喜びを感じてほしい。
もう一度、声を大にして言いたい。 「甲子園に出場できない選手のほうが大多数なのだから」
☆甲子園意外に分散開催さはどうなのか?
最近、甲子園大会の日程のことが議論されている。
将来ある選手の、特に投手の体を酷使していいのか?
日程に無理がないか?
大阪ドームやGS神戸、そして甲子園の3球場を使えばいいではないか?
(※大阪ドーム=京セラドーム GS神戸=ほっともっとスタジアム 便宜上、大阪ドーム・GS神戸とする)
準々決勝から甲子園一本ですれば、日程が平等に消化できるではないか?
⇒そう、上記の意見はすべてごもっともなのです。
☆サッカーやラグビーは?
高校総体に関しては、各県(地域)持ち回り。
冬の選手権は、サッカーが首都圏開催。準決勝から国立競技場。
ラグビーの春の選抜大会は埼玉県熊谷市。
冬の選手権は東大阪市の「花園」
この「花園」はグラウンドが3面ある。
メインスタジアム。第2グラウンド。第3グラウンド。
サッカーもラグビーも1回戦を2日に分けて実施。
その後、2回戦~決勝。しめて6日か7日で大会が終わる。(ラグビーは試合ごとに1日休養日がある)
☆では、高校野球は?
一日4試合を甲子園球場のみで開催。
なので、組合せ上、大会7日目に初戦を迎えるチームもある。
7日目が初戦のチームは初戦が2回戦になる。
9日目に3回戦。 11日目に準々決勝。 12日目に準決勝。 13日目に決勝。
約一週間の間に5試合することになる。
確かに「超ハード」
分散開催もうなずける。 が・・・が・・・である。
☆やっぱり甲子園なんですよね~
高校球児は甲子園を目指しているんですよね~
決して、大阪ドームやGS神戸をどうこう言っているのではない。
歴史が違う。
果たして、自分が現役のときに、仮に甲子園出場が決まって、甲子園以外で試合したらと思うと・・・
なんだか、拍子抜けする。
分散開催も一理ある。
しかし、それを凌駕するものが「甲子園球場」にある。
球児としては、たとえ、大会7日目が初戦となっても、甲子園で試合をしたいだろうな。
したいはず。元球児として断言できる。
☆酷暑なのでドームは?
大会自体を秋に・・・という声があるが、これはちょっと無理だろう。それこそ分散開催になる。
勝手に思っているだけだが、「夏」「甲子園」「高校野球」は日本の文化のような気がする。
グラウンドキーパーの方にはご苦労をかけるが、一日5試合はどうだろう?
第1試合(7時) 第2試合(10時) 第3試合(13時) 第4試合(16時) 第5試合(19時)
投手の投球間隔も制限。タイムの回数も制限。試合のスピーディー化を図る。
そして、休養日をしっかり設ける。
投手の球数制限はもちろん実施。
さらには、阪神タイガースには「死のロード」にはまって行ってもらう。(笑)
ということで、私的には、やっぱり「甲子園球場」なんですね~というふうに結論つけたいと思います。
でも、いろいろ試してみることでしょうね。確かに暑い。
夏の高校野球が始まった。
元高校球児としては血が騒ぐ時期だ!
まずは、大会に出場された高校・選手には素直にお祝いを言いたい。
さらに、甲子園球場でプレーができる幸せを感じてほしい。
私は甲子園には出場していない。ハッキリ言って、出場できない選手のほうが圧倒的に多いのである。
甲子園に出場しただけで羨ましい。 だからこそ、楽しんでプレーしてほしい。
学校・郷土の期待はいやおうなしにあるだろうが、まずは選手自身が甲子園でプレーできる喜びを感じてほしい。
もう一度、声を大にして言いたい。 「甲子園に出場できない選手のほうが大多数なのだから」
☆甲子園意外に分散開催さはどうなのか?
最近、甲子園大会の日程のことが議論されている。
将来ある選手の、特に投手の体を酷使していいのか?
日程に無理がないか?
大阪ドームやGS神戸、そして甲子園の3球場を使えばいいではないか?
(※大阪ドーム=京セラドーム GS神戸=ほっともっとスタジアム 便宜上、大阪ドーム・GS神戸とする)
準々決勝から甲子園一本ですれば、日程が平等に消化できるではないか?
⇒そう、上記の意見はすべてごもっともなのです。
☆サッカーやラグビーは?
高校総体に関しては、各県(地域)持ち回り。
冬の選手権は、サッカーが首都圏開催。準決勝から国立競技場。
ラグビーの春の選抜大会は埼玉県熊谷市。
冬の選手権は東大阪市の「花園」
この「花園」はグラウンドが3面ある。
メインスタジアム。第2グラウンド。第3グラウンド。
サッカーもラグビーも1回戦を2日に分けて実施。
その後、2回戦~決勝。しめて6日か7日で大会が終わる。(ラグビーは試合ごとに1日休養日がある)
☆では、高校野球は?
一日4試合を甲子園球場のみで開催。
なので、組合せ上、大会7日目に初戦を迎えるチームもある。
7日目が初戦のチームは初戦が2回戦になる。
9日目に3回戦。 11日目に準々決勝。 12日目に準決勝。 13日目に決勝。
約一週間の間に5試合することになる。
確かに「超ハード」
分散開催もうなずける。 が・・・が・・・である。
☆やっぱり甲子園なんですよね~
高校球児は甲子園を目指しているんですよね~
決して、大阪ドームやGS神戸をどうこう言っているのではない。
歴史が違う。
果たして、自分が現役のときに、仮に甲子園出場が決まって、甲子園以外で試合したらと思うと・・・
なんだか、拍子抜けする。
分散開催も一理ある。
しかし、それを凌駕するものが「甲子園球場」にある。
球児としては、たとえ、大会7日目が初戦となっても、甲子園で試合をしたいだろうな。
したいはず。元球児として断言できる。
☆酷暑なのでドームは?
大会自体を秋に・・・という声があるが、これはちょっと無理だろう。それこそ分散開催になる。
勝手に思っているだけだが、「夏」「甲子園」「高校野球」は日本の文化のような気がする。
グラウンドキーパーの方にはご苦労をかけるが、一日5試合はどうだろう?
第1試合(7時) 第2試合(10時) 第3試合(13時) 第4試合(16時) 第5試合(19時)
投手の投球間隔も制限。タイムの回数も制限。試合のスピーディー化を図る。
そして、休養日をしっかり設ける。
投手の球数制限はもちろん実施。
さらには、阪神タイガースには「死のロード」にはまって行ってもらう。(笑)
ということで、私的には、やっぱり「甲子園球場」なんですね~というふうに結論つけたいと思います。
でも、いろいろ試してみることでしょうね。確かに暑い。
☆熊本のビアレストラン老舗「オーデン」
ビールが美味しい季節!
ランニングしているものの、晩酌(ビール)の誘惑には負ける日々。(^o^)
先日、とある会合に出席し、納涼会という名目で「オーデン」に行った!
ホント、熊本の老舗のビアレストラン!
美味しい本格的なビールが楽しめる!
お店のHP ↓
http://www.beer-oden.com
まずは、美味しいビールの画像をとりあえず。^_^

ビールと泡のゴールデンラインです。基本中の基本。
しかし、その基本を忠実に徹底するところにお店の長年の支持があるのだろう。
☆ウインナーもお薦め!
コースターは持って帰りたくなる!

お店の外看板は変わりません。

肝心な料理も美味しい。
特にお薦めは本場ドイツからの豊富なウインナー!

カリッという食感。
ビールとのマッチ感。
オーデンに来たら注文しないといけません。
☆その他の料理も美味い!
当日頂いた料理がコチラ ↓

生ハムサラダ。

グリッシーニ。

トウキビ。(とうもろこし)

魚料理。白身魚とホタテ!

ピザ!
どれも美味しく、ビールが進むくんでした〜
個人的に、オーデンには20年ぶりくらいに行った。
変わらぬビールへのこだわり。嬉しいですね。
造り手と消費者を結ぶ重要な役割に誇り・プライドを感じた。
ユニフォームの蝶ネクタイが物語っている。
このようなお店は未来永劫残ってほしい。
ビールが美味しい季節!
ランニングしているものの、晩酌(ビール)の誘惑には負ける日々。(^o^)
先日、とある会合に出席し、納涼会という名目で「オーデン」に行った!
ホント、熊本の老舗のビアレストラン!
美味しい本格的なビールが楽しめる!
お店のHP ↓
http://www.beer-oden.com
まずは、美味しいビールの画像をとりあえず。^_^

ビールと泡のゴールデンラインです。基本中の基本。
しかし、その基本を忠実に徹底するところにお店の長年の支持があるのだろう。
☆ウインナーもお薦め!
コースターは持って帰りたくなる!

お店の外看板は変わりません。

肝心な料理も美味しい。
特にお薦めは本場ドイツからの豊富なウインナー!

カリッという食感。
ビールとのマッチ感。
オーデンに来たら注文しないといけません。
☆その他の料理も美味い!
当日頂いた料理がコチラ ↓

生ハムサラダ。

グリッシーニ。

トウキビ。(とうもろこし)

魚料理。白身魚とホタテ!

ピザ!
どれも美味しく、ビールが進むくんでした〜
個人的に、オーデンには20年ぶりくらいに行った。
変わらぬビールへのこだわり。嬉しいですね。
造り手と消費者を結ぶ重要な役割に誇り・プライドを感じた。
ユニフォームの蝶ネクタイが物語っている。
このようなお店は未来永劫残ってほしい。